Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/r4103239/public_html/fujikenapr06blog.com/wp-content/plugins/rich-table-of-content/functions.php on line 490
明けましておめでとうございます。ふーじーです。
本年も何卒宜しくお願い致します。
昨年は、あまりブログの更新が出来ていませんでしたので、今年のブログの目標は
月に2回以上は更新をするようにしていきます(キッパリ)
今年の本格的な目標は『資格の勉強』と『資格の取得』です。
では、仕事とプライベートで分けてどんな資格を取得していきたいかと言うと・・・
業務上の必要な資格は
1.社会保険労務士
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
2.建設業経理事務士2級
建設業経理士検定試験は、登録経理試験の実施機関として国土交通大臣の登録を受け、建設業振興基金が実施する検定試験です。建設業者が健全な発展を図るうえで、適正な経理と計数を行うことは必要不可欠である一方、建設業は受注産業であり会計処理に特殊な点が多いことから、財務・経理の担当者は高い専門性が求められます。その建設業経理に関する知識の向上を図ることを目的としています。中でも1級、2級合格者は、公共工事の入札可否の判断の資料となる経営事項審査の評価対象の1つになっています。
3.第一種衛生管理士
衛生管理者は、労働者の健康障害や労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた国家資格です。50人以上の労働者がいる職場では、衛生管理者を選任しなければなりません。衛生管理者の主な仕事は、作業環境の管理、労働者の健康管理、労働衛生教育の実施、健康保持増進措置などです。少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
4.マイナンバー保護士
法人・個人事業主は、雇用している従業員のマイナンバーを集めて管理しますが、その際、事業主にはマイナンバー情報の漏洩を防ぐ義務があります。そこで、マイナンバー保護士の業務は、担当者1人1人にマイナンバー制度の目的や仕組みを理解して業務にあたるようにリーダーシップを取る事です。したがって、マイナンバー保護士は、マイナンバー実務検定の上位資格となります。法人が従業員のマイナンバーを管理する目的は、給与事務、法定調書の作成のためですが、マイナンバー保護士は、実務に於いて、個人番号を取得する際の利用目的の通知・公表することや、法を逸脱した様々な行為や管理ミスが発生しないように、厳正に業務が遂行されるように担当者を指導する必要があります。なお、今後はマイナンバーの利用範囲が金融や医療の分野などにも広げられる見通しです。マイナンバー保護士は最新の動向を理解しておく事も重要です。
プライベートで取得したい資格は
1.社会保険労務士 ※業務上と同様
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
2.FP(ファイナンシャルプランナー)2級
ファイナンシャルプランナーは、主にお客様の資産運用の相談に応じ、貯蓄計画・投資計画・相続対策・保険対策・税金対策などといった総合的な資産設計や運用法をアドバイスするスペシャリストである。他人の大切な財産の運用法を勧めるため、最新の金融知識をはじめ、不動産や法律などについての深く正確な知識が求められる。また、顧客の意向を最大限かつ正確にくみ取れるヒアリング力や、顧客が不快感や抵抗感を持たずに相談できる人柄、正義感などを持ち合わせ、顧客からの信頼を得られなければ行えない仕事である。この仕事を行うためにはファイナンシャルプランニング技能士(FP資格)やファイナンシャルプランナー資格(AFP資格・CFP資格)等の資格取得が望ましい。ファイナンシャルプランナーとして有名になれば雑誌などへの執筆やセミナーなども行い活躍の場はかなり拡がってくるだろう。
3.宅建士
宅建や宅建士とは「宅地建物取引士」の略称で、国家資格にあたります。そして、この宅建士になるための資格試験を「宅建試験」といいます。宅建士とは、「宅地建物取引業者」で働く従業員をイメージされると良いでしょう。宅地建物取引業者とはいわゆる不動産会社のことで、土地や建物の売買、賃貸物件のあっせんなどを行っています。不動産取引はとても高額です。お客様の多くは不動産に関する専門知識や売買経験がほとんどないため、不当な契約を結んでしまうと思わぬ損害を被ることがあります。そのようなことがないよう、お客様が知っておくべき事項(重要事項)を説明するのが宅建士の仕事。そして、重要事項の説明をお客様にできるのは宅建士だけです。宅建とは、不動産取引の専門家を示す資格、といえるでしょう。宅建資格を得て宅建士の仕事をするためには、まず宅建試験に合格し、合格後は試験開催地の都道府県知事に対して登録手続きを行い、取引士証の交付を受けることが必要です。しかし宅建試験の合格率は低く、例年15~17%台となっています。難易度が高いため、合格するためには専門的な勉強が必要です。独学で受験する方もいますが、専門的な勉強が必要であることから、専門学校や通信講座を利用する人が多い傾向にあります。
4.不動産実務検定2級
J-RECの不動産実務検定®は、健全な経営を実現したい大家さん、これから不動産投資によって安定した将来を実現したい方、また、より高度なコンサルティング技能を身につけ顧客に安心したサービスを提供したい建築不動産関係の方のために不動産運用にまつわる実践知識を体系的に網羅した日本初の不動産投資専門資格です。全国各地の認定講座でライフプランニング、不動産投資、満室経営、税金対策、建築、ファイナンス、土地活用コンサルティングなど幅広い知識を学ぶことができます。
では、どれから取得するのか
結論は、FP2級からにします。仕事でも役に立つし、プライベートでも役に立つし、それにFP3級を取得しているので上位資格を目指すことにします。あと、FPの勉強と社労士の勉強って似ているところもあるので、FPの勉強はきっと社労士の勉強にも活かされるはず!
他にもFPの勉強は宅建士にも活かせれる部分もあるし、宅建士の勉強は不動産実務検定に繋がるし、全ては繋がっていて無駄なことは何一つもないということです。
では、正月はゆっくり過ごして、仕事始まりと同じくらいから少しずつ勉強を始めていきましょう!
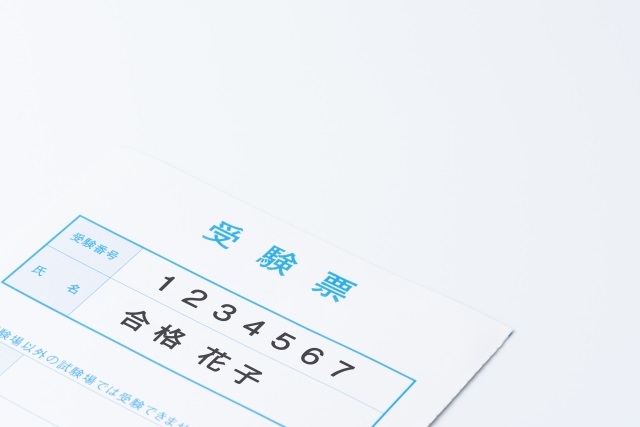


コメント